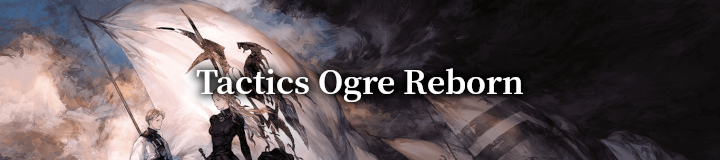バフカードはタクティクスオウガ リボーンで新しく追加されたシステム。ランダムでフィールドにバフカードが出現し、取得したユニットをそのバトル中だけ強化する。
ここではバフカードの種類と効果、メリットとデメリットについて解説する。
バフカードはステータスを恒久的に上昇させるカード(タロットカード)とは別物。タロットカードもしっかりと登場するこのページでは触れていない。
パフカードではなく『バフ』カード。半濁音ではなく濁音。バフとは補助効果・強化効果のこと。
バフカードの種類と効果
| バフカード | 効果 |
|---|---|
| 直接攻撃のダメージが1.5/2.0/2.5/3.0倍になる。 | |
| 魔法攻撃のダメージが1.5/2.0/2.5/3.0倍になる。 | |
| クリティカル率が上昇する。クリティカルするとダメージは約2倍に上昇。 | |
| MPの回復速度が上昇する。 0:WT18で2回復 1:WT18で4回復 2:WT18で6回復 3:WT18で8回復 4:WT18で10回復 | |
| オートスキルの発動確率が上昇する。3つ取得でほぼ確実にオートスキルが発動。 |
直接攻撃は、武器攻撃、スペシャル、必殺技、アイテム(爆弾とオーブ)が該当。バフカードは複数取得すると効果が増強される。
バフカードはユニット1体につき4つまで取得可能。4つ目以降を取得すると、最も古いバフカードが押し出されて破棄される。例:直接攻撃x1 → スキル発動x3と取得した後、MP回復のバフカードを取ると最初に取得した直接攻撃のバフカードがなくなる。

バフカードのメリットとデメリット
- 効果が高く純粋にロマンがある
- 戦略的に活用できる
- 出現頻度が非常に高い
- 特定の戦術と相性が良くない
効果が高く純粋にロマンがある
バフカードは攻撃面の強化効果が多い。効果自体は非常に強力でロマンがある。
- 攻撃力アップ
- 魔法攻撃力アップ
- クリティカル率アップ
- スキルの発動率上昇
クリティカル確率上昇のバフはかなり効果が高い。前作ではクリティカルのダメージ倍率は1.5倍だったが、タクティクスオウガリボーンでは2倍に上昇している。
攻撃力上昇のバフカードは1つ取るだけでダメージは1.5倍近く上昇する。ウォリアーのマイティインパクトと組み合わせると3倍のダメージを叩き出す。挟撃やカウンターを使うとをより有効にバフカードを活用できる。

戦略的に活用できる
バフカードは木箱等の障害物を壊すと出現する。スタート位置の近くに木箱や草があるとき投石で破壊してバフカードを取得しよう。
また、敵リーダーを狙撃して速攻を決めたいときや、救出戦で突撃するときにもバフカードは役立つ。サモンダークネスを使ってくる敵を瞬殺したいときに攻撃的なバフカードはとても便利。単発の攻撃では火力が足りていなくても、スキルとバフカードを合わせるとダメージが爆発的に上昇する。
出現頻度が非常に高い

戦場に咲き乱れるバフカード。戦略的に活用しやすいのは良いことだが、ときどき大量発生して少し邪魔になる。バフカードが出現したタイルは地面を焼けず、埋もれた財宝を妨害する。この点はデメリットかもしれない。
特定の戦術と相性が良くない
バフカードの出現位置がすべての戦略にマッチするわけではない。
見ての通りバフカードが出現するのは前線付近。後衛が楽に取得できる位置にはほどんど出現しない。前に進まなければバフカードは取得できず籠城戦術と相性が悪い。
バフカードは立て籠もりよりも積極的な前進を薦めているように見える。
バフカードはなぜ導入されたのか?
タクティクスオウガ リボーンのバフカードはなぜ導入されたのか? バフカードの目的について考察。
以下の内容は考察です。
AI行動のパターン化を防ぐ
割とありきたりだが、バフカードによって環境を変化させ、AI行動のパターン化を防ぐ。
前作の乱数依存の高いAIよりも、環境を基準にして判断した方が明確な意思を持ったAIが生まれる。これは、AI自体の一貫性を保ちつつランダム性も付与できるメリットがある。
簡単に言うと、
今作のAIは行動に乱数を(あまり)使っていない?
チャリオットの行動変化には何かしらAIの行動を変える理由が必要なので、バフカードがその役割を担ったのではないかという推測。
前作のAIは乱数によって行動を変えていたので、バフカードのようなシステムは必要なかった。しかし、乱数依存のAIは明らかに行動が不可解。なぜ殴れるのに何もしないのか? なんてことがよく起こっていた。
何をするか分からない知能の無いAIよりも意思が明確な賢いAIの方がゲームは面白い。しかしそれはチャリオットと矛盾してしまう。
そうして生まれたのがバフカードなのではないかと。AIではなくバフカードを乱数で操作する。こうすることでAIもチャリオットも救われる。
・・・という妄想を初期の頃にしていた。しかし・・・。
バフカードはプレイヤーの行動を変化させる
実際にゲームをプレイしてみると、バフカードは確実にプレイヤーの行動を変化させる。
バフカードによって劇的に変化する戦況に対応する必要があるからだ。
特に気にしていなかった敵ユニットが、攻撃力アップのバフカードを複数取って強ユニットに変わったり、クリティカル率が変化し劇的なダメージを与えたり。これらは予測できず、その都度状況に対応する必要がある。
例:味方が負傷して形勢が不利 → 殲滅からリーダー狙いに切り替える。バフカードを複数拾った味方が敵を次々と蹂躙する。
バフカードが発表されたときの「バフカードを取り合い、動的に変化する状況にどう対応するか考えながら進めることが本作ならではのバトルの醍醐味」と説明されていたが、確かにその通りだと思う。
バフカードは間違いなくタクティクスオウガリボーンの戦闘デザインの根幹を成している。バフカードは、AIの行動ではなくプレーヤーの行動を変化させている。